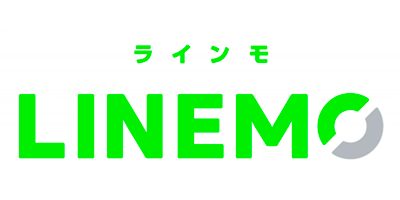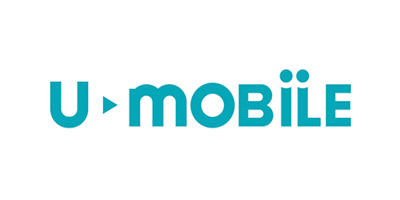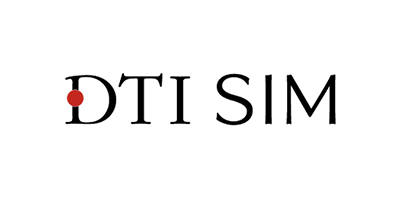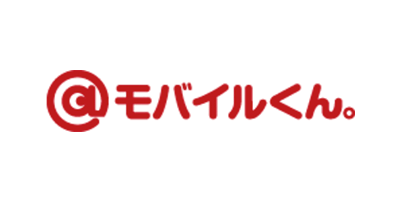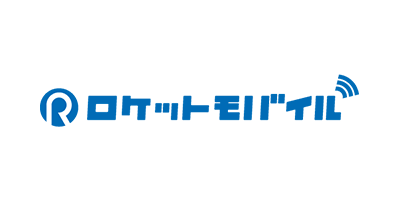Nexus 6は果たして「買い」か? スペックなどを比較

Googleの「Nexus 6」は2014年12月に発売されたSIMフリースマホ。当時で大人気の端末でした。Nexus 6の詳細と、ASUSの「ZenFone 2」、Huawaiの「Ascend Mate7」といったライバルモデルとスペックや価格、特徴などを比較しています。
この記事の目次
Googleから2014年12月に発売された「Nexus 6」がSIMフリースマホ市場で大人気でした。発売直後は品切れ状態が続き、オフィシャルの「Googleストア」でも注文してから届くまでに3週間から5週間もかかるという状況でした。Nexus 6がそれほどまでに人気を集めた秘密はどこにあったのでしょうか。
今回はNexus 6の詳細と、当時のライバルモデルだったASUSの「ZenFone 2」、Huawaiの「Ascend Mate7」とスペックや価格、特徴などを比較してみたいと思います。
Nexus 6とはどんなモデルだったのか
まずはNexus 6の特徴からご紹介しましょう。
Nexus 6はmotorolaと共同開発した6インチファブレット

出典:ソフトバンク株式会社
Nexus 6(ネクサス 6=シックス)はあのGoogleとアメリカのmotorolaが共同で開発したSIMフリースマホです。SIMロックがかかっていない端末なので、当然、格安SIMを自由に使うことができます。日本以外の国では2014年11月に、日本では12月に発売されました。Googleのリファレンスモデル、Nexusシリーズの第6世代目ということになります(後述)。
画面が5.96インチと当時のスマートフォンの中では大きいサイズであることから、スマートフォンとタブレットの中間である「ファブレット」と扱われることもあったようです。Android5.0(Lollipop)が搭載される初のモデルとなります。
販売していたのはGoogleの公式ショップ「Googleストア」と、ワイモバイルです。
SIM無しで買いたい場合はGoogleストアで買う必要があります(2019年1月現在、取り扱い終了)。もちろんAmazonやいわゆる白ロム端末を販売しているショップ等でも購入することはできますが、これらは並行輸入品(海外向け仕様)が多い点に注意が必要です。
ストレージが32GBのモデルと64GBのモデルがあり、Googleストアでの値段はそれぞれ7万5,170円、8万5,540円、ワイモバイルでは7万5,168円と8万5,536円でした。2019年1月現在、Amazonでは並行輸入品の新品やワイモバイルで販売されていた端末の白ロムが、半額程度やそれ以下の価格で販売されています。
Nexus 6のスペックを確認
| Nexus 6 | |
|---|---|
| OS | Android 5.0(lolipop) |
| ディスプレイ | AMOLED 5.96インチ 2560×1440 |
| CPU | Snapdragon 805 2.7GHz クアッドコア |
| RAM | 3GB |
| 内蔵ストレージ | 32GB/64GB |
| 対応メディア | - |
| おサイフケータイ | × |
| 防水/防塵 | -/- |
| ワンセグ/フルセグ | × |
| カメラ | 前面200万画素 背面1300万画素 |
| サイズ(H×W×T) | 159.26mm x 82.98mm x 10.06mm |
| 重さ | 184g |
| バッテリー | 3220mAh |
| カラーバリエーション | ダークブルー、クラウドホワイト |


どのくらいおトクなの?
をもとに算出
プランをみつけよう
Nexus 6は「リファレンスモデル」
Nexus 6のことを調べているとよく「リファレンスモデル」という言葉が出てくると思います。「リードデバイス」という言葉を使う場合もあります。
一般的にリファレンスモデルというのは商品開発の現場で使われる言葉で、日本語に訳すと「実装参照デバイス」という意味になります。
例えばAndoroid端末上で動くアプリ等のさまざまな開発を行うにあたって、Googleが公開しているAndroidの仕様書を見ながら開発を行うだけではどうしても不十分で、実際にAndroid上で動かす必要があります。しかもそのAndroidを搭載した端末は、Android以外の機能を極力排除した「純粋な」端末であることが望ましく、NexusシリーズはそのためにGoogleが用意している端末です。Androidのバージョンアップがあると必ず最新のリファレンスモデルが真っ先にその対象になります。アプリ等を開発する現場としては、リファレンスモデル上で正常に動作すれば「リリースしても問題ない」という判断に至るわけです。
このような性格上、Nexusシリーズの端末にはプリインストールされているアプリなどはほとんどありません。通常、例えばXperiaシリーズを買えばソニーの、Galaxyシリーズを買えばサムスンのアプリがたくさんプリインストールされていますし、それをdocomoやauといったキャリアを通じて買えばさらにキャリアのアプリもプリインストールされています。しかしNexusシリーズはこういったことが一切ありません。そのため、シンプルな端末を求める人の中には、好んでNexusシリーズを買い続ける人も数多くいます。
Nexus 6とライバルを徹底比較
それでは続いてNexus 6と、日本市場でシェアを伸ばしているASUSのZenFone 2、HuaweiのAscend Mate7という「最強SIMフリースマホ」3モデルを比較してみることにしましょう。
まずはスペックの比較から
| Nexus 6 | ZenFone 2 | Ascend Mate7 | |
|---|---|---|---|
| OS | Android 5.0 (Lollipop) | Android 5.0 (Lollipop) | Android 4.4 (KitKat) |
| ディスプレイ | AMOLED 5.96インチ 2560×1440 | IPS液晶 5.5インチ 1920×1080 | IPS-NEO液晶 6インチ 1920×1080 |
| CPU | Snapdragon 805 2.7GHz クアッドコア | Intel Atom Z3580 2.3GHz クアッドコア | Hisilicon Kirin 925 1.8GHz / 1.3GHzオクタコア |
| RAM | 3GB | 4GB | 2GB |
| 内蔵ストレージ | 32GB/64GB | 16GB/32GB/64GB | 16GB |
| 対応メディア | - | microSDXC (最大64GB) | microSD (最大32GB) |
| おサイフケータイ | × | × | × |
| 防水/防塵 | -/- | -/- | -/- |
| ワンセグ/フルセグ | × | × | × |
| カメラ | 前面200万画素 背面1300万画素 | 前面500万画素 背面1300万画素 | 前面500万画素 背面1300万画素 |
| サイズ(H×W×T) | 159.26mm x 82.98mm x 10.06mm | 152.5mm× 77.5mm× 10.9mm | 157mm× 81mm× 7.9mm |
| 重さ | 184g | 170g | 185g |
| バッテリー | 3220mAh | 3000mAh | 4100mAh |
| カラーバリエーション | ダークブルー、クラウドホワイト | グラシアグレー、オスミウムブラック、グラマーレッド、セラミックホワイト、シアーゴールド | オブシディアン・ブラック 、ムーンライト・シルバー |
Ascend Mate7はオクタコア搭載
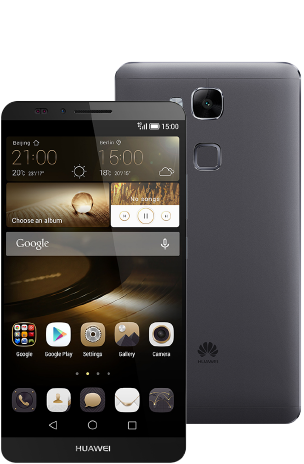
出典:楽天モバイル
比較表を上から眺めていって真っ先に気がつくのは、Nexus 6とZenFone 2のCPUが「クアッドコア」なのに対してAscend Mate7が「オクタコア」となっている点でしょう。
スマホのスペック表などを見るとよく目にする「CPU」という言葉ですが、これは「Central Processing Unit」の略で日本語に直すと「中央演算処理装置」となります。いわばスマホの「脳みそ」にあたるパーツです。「2.7GHz」とか「2.3GHz」という数字は「クロック数」と言われるものですが、数字が大きいほど頭が良い、と考えておけばよいでしょう。
そして「コア」とはCPUの中心部分、「脳みその中の脳みそ」とも言える部分です。元々CPUの中にコアは1つしかありませんでしたが、やがて技術の進化で2つのコアが存在するものが登場しました。これを「デュアルコア」といい、コアが4つあるものを「クアッドコア」といいます。6つだと「ヘキサコア」、8つだと「オクタコア」といいます。つまりNexus 6とZenFone 2はコアが4つなのに対してAscend Mate7はコアが8つある、ということになります。「1.8GHz/1.3GHz 」となっているのは、「1.8GHzが4コア」「1.3GHzが4コア」という意味です。
もちろんコア数が多いほうが高性能であることは間違いないでしょう。オクタコアが搭載されているスマホは非常にサクサクと動きます。クアッドコアに比べて倍のコアで作業をしているわけですから当然の話しです。しかしクアッドコアに比べてそれほど劇的な違いがあるか、というと、必ずしもそうではないような気もします。電車に例えるならば各駅停車と急行の差程度です。決して在来線と新幹線のような差ではないと思います。つまりAscend Mate7とNexus 6、ZenFone 2の差もそのくらいだと考えておくのが妥当でしょう。
クアッドコアとオクタコアでもっとも大きな差が出るのは「バッテリーの持ち」だと思います。同じ作業を4つのコアでこなすのと8つのコアでこなすのとでは、前者のほうがバッテリーをたくさん消費するからです。
バッテリーの容量を比較してもAsend Mate7は4,100mAhと非常に大容量になっていますが、オクタコアであることも考えるとバッテリーの持ちが非常に良いということが考えられます。
Nexus 6は外部メディア非対応
ZenFone 2はmicroSDXCに、Ascend Mate7はmicroSDにそれぞれ対応しているのに対して、Nexus 6は外部メディアに対応していません。つまりSDカード等を挿して使うことができません。その代わり内蔵ストレージとして最大64GB用意されています。
64GBで足りるか足りないかは人それぞれなので何とも言えません。大容量の動画や高画質の画像を大量にスマホに入れておきたい、という人にとっては足りないかもしれませんが、最近ではDropboxやGoogleドライブのようなオンラインストレージがたくさんありますし、それぞれスマホからでも簡単にアクセスできるようにアプリが用意されています。こういったサービスを組み合わせればただちに容量不足になるようなことはないと思います。
ただ、パソコンからスマホにデータを移す際に外部メディアがあった方が便利なのは間違いないです。外部メディアがないとパソコンとスマホをケーブルでつなぐか、メールに添付するか、オンラインストレージを経由するかをしなければならず、どちらも多少面倒です。頻繁にデータの出し入れをする場合はネックになってくるでしょう。
この点、ZenFone 2は内部ストレージで64GB、外部メディアで64GBの合計128GBのデータを入れて持ち歩けるというのは大きなアドバンテージでしょう。
防水・防塵対応ではない
今回比較しているNexus 6、ZenFone 2、Ascend Mate7のいずれもが防水・防塵に対応していません。正しくは防水・防塵の対応状況について、規格や等級について正式にアナウンスされていない、と言ったほうがいいかもしれません。
最近では多くのスマホが防水・防塵対応であることを謳っており、スペック表などを見ても「IPX5/8・IP5X」といったような記載をよく見かけると思います。この防水や防塵に関する規格はJIS(日本工業規格)によって定められており、保護の程度によって8つの等級に分類されています。つまり「IPX5/8・IP5X」といった表記はJISで定められた基準のうちどの程度のものを満たしているかを表すものです。
防水・防塵性能が発表されていないということは、少なくともアピールするほどの性能は持ち合わせていない、ということでしょう。多少雨に濡れた程度であれば問題ないとは思いますが、どの程度の水や埃であれば大丈夫なのか、という基準が示されていないのは、外での使用が多い人にとっては気になるところです。
ちなみに2015年春に発売された「Xperia J1 Compact」は防水・防塵性能が「IPX5/8・IP5X」と発表されていますが、これは防水が「外側から水を掛けられた場合の保護性能が5」(内径6.3㎜の注水ノズルを使用し、約3mの距離から12.5L/分の水を最低3分間注水する条件であらゆる方向から噴流を当てても、通信機器としての機能を有する)「水に沈めた場合の保護性能が8」(常温で水道水、かつ静水の水深1.5mのところに携帯電話を沈め、約30分間放置後に取り出したときに通信機器としての機能を有すること)、防塵が「5」(粒径75μm以下の塵埃が入った装置に8時間入れて取り出したときに通信機器の機能を有し、かつ安全を維持すること)という意味になります。
Nexus 6の価格はやや高いか?
最後にNexus 6、ZenFone 2、Ascend Mate7の端末価格を比較してみましょう。(発売当時の参考価格)
| Nexus 6(64GB) | 8万5,536円 |
| ZenFone 2(64GB) | 5万4,864円 |
| Ascend Mate7(16GB) | 5万2,800円 |
Nexus 6はワイモバイルで64GBモデルを購入する際の価格です。ZenFone 2は内蔵ストレージが64GBモデルでこの価格。スペック的にも申し分がないので、非常にコストパフォーマンスの優れたモデルと言えます。
気になるのはNexus 6は8万円台ということ。Androidを作っているグーグルが直接開発に携わったリファレンスモデルということを差し引いても「やや高い」と言わざるを得ません。しかしAndroidの最新バージョンを真っ先に使うことができるなど、スマホ好き、ガジェット好きにとっては魅力的なモデルです。好きな人にとっては「買い」ですが、それほど大きなこだわりがなければZenFone 2のほうが手頃感がありおすすめです。
Nexus 6は当時では価格設定が高めの端末だった
今回ご紹介したNexus 6やZenFone 2、Ascend Mate7など、2014年から2015年は素晴らしいSIMフリースマホがたくさん登場するようになった頃でした。SIMフリースマホはキャリアで購入するスマホと違って当時は端末購入サポートのようなものがあまりなかったため、価格が高くなりがちなのがやや難点でしたが、MVNOの格安SIMを使うことを考えるとトータルで見ればむしろ安くなる場合もあります。今までのにキャリアに縛られるのではなく、端末もSIMも自由に乗り換えることができる時代になったのは消費者にとっては喜ばしいことですね。